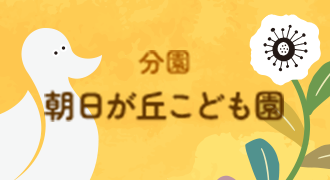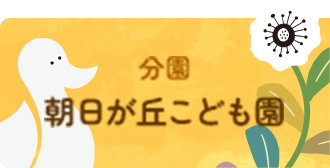子どもだけではなく保護者の方にも寄り添いたい
2005年入職(保育教諭20年目)
年少フリー担当
仕事の内容は?
現在は年少クラスを担当しています。担任ではなくフリーという立場で、子どもたちや担任の先生のサポートを行っています。出勤後、まずはクラスのお部屋にいき、早く登園している子の荷物整理を一緒にしたり、子どもたちの様子を見ながら、『ちょっと元気がないな~』と思ったら、元気が出るよう声がけをしたりしています。
その後の主活動は担任の先生が中心に行うので、私はそのサポートです。昨年の11月末に育休明けで職場復帰してから、フリーという立場で仕事をさせてもらっています。
入職のきっかけは?
私は4人姉弟の一番上で、2歳下に妹、4歳下に弟、さらに14歳下に弟がいます。私が中学2年生の時に一番下の弟が産まれたのですが、その弟の世話をしている中で、『赤ちゃんのお世話って楽しい』と思うようになり、楽しいことを仕事に出来たら良いなと思ったのが最初のキッカケでした。
他にも、ママさんバレーをしていた母親に付き添って、夜の練習に出かけたりしていたのですが、他にもママさんと一緒に子どもたちが来ていて、一緒に遊んだりしている中で、改めて子どもと遊ぶことの楽しさを実感し、この道に進もうと思いました。


3児の子育てと仕事を両立できる環境
3人の子どもは、一番の上の子が年中、真ん中の子が3歳、一番下の子が1歳です。3人とも当園に通っているので、子どもと一緒に出勤し、一緒に退勤しています。日中は、信頼できる先生方に子どもたちをお任せしているので、安心して仕事に集中できています。
また、産休・育休の制度がしっかりしているのはもちろん、復帰後の柔軟な対応にも助けられています。担任を持たず、フリーという立場で働かせていただいているので、子どもの急な体調の変化にも対処できています。子育てママにとって、とても働きやすい環境だと思います。
仕事のやりがいは?
子どもの成長を間近で見られることですね。お母さんたちよりも先に成長が見られることに申し訳ないという気持ちもありながら、同時に嬉しさを感じています。ずっと泣いて登園していた子が、ある日突然、泣かずに登園できるようになったり、今までできなかったことが練習を重ねてできるようになったり…。子どもの力ってすごいなというのと、この場に立ち会えている自分は幸せだなと感じています。
また、私自身も3人の子を持つ母親ですが、母になる前と後では、その考え方も変わりましたね。母になる以前は、子どもの成長が何より嬉しかったのですが、自身も母になると、ご家族の方に成長を報告した際、とても喜んでくれる姿を見られることも嬉しいと感じるようになりました。
「国際バカロレア」の活動について
当園で取り組みを始めたのをキッカケに「国際バカロレア教育」について知りました。その言葉を聞いたとき、とても難しいことをしなければいけないのでは…と、少し不安になりましたが、研修を受けることで、その不安はすぐに解消されました。
同時に、保育への考え方が大きく変わりましたね。「国際バカロレア教育」を実践する前は、“集団生活に慣れさせる”、“やるときはみんな一緒にやる”という型にはまったものでしたが、集団の中に入りたくない子もいれば、みんなと同じことをやりたくない子もいる、その子らしさの表現を大事にできるようになりました。これは子どもだけではなく、先生たちも同じです。保育教諭はこうでなければいけないというものから、自分は自分でいいという考え方に変わりました。肩の力を抜いて、保育と向き合えるようになりましたね。多様性の時代に合った教育プログラムだと思います。


今後の目標は?
お父さんやお母さんより、私たち保育者の方が子どもたちと接する時間が長いと思います。そのような中で、日々の些細な変化に気づくことはもちろん、良いことも・悩んでいることもしっかり共有すること。保護者の方に寄り添える保育者になりたいですね。自分も子どもを持つ母親だからこそ、子どもだけではなく、保護者にとっても近い存在でありたいと思います。

この記事は2025年3月時点の内容です